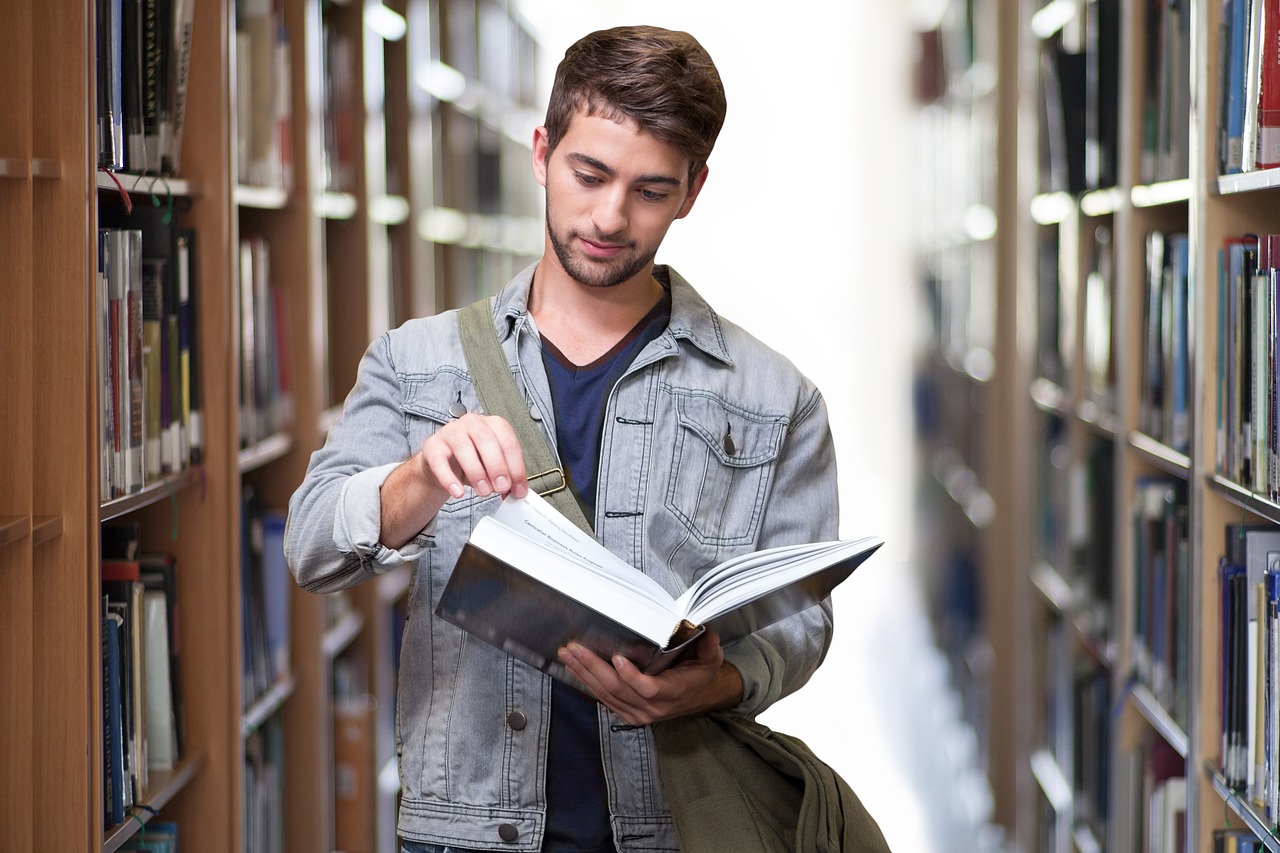今回は書評です。
リサーチ・ドリブン・イノベーション - 「問い」 を起点にアイデアを探究する (安斎勇樹, 小田裕和) をご紹介します。
✓ この記事でわかること
- 本書の概要
- マーケティングリサーチとイノベーションの組み合わせ
- 全ては 「問いの設計」 から始まる
- 多数決ではなく 「多様決」
- リサーチドリブンイノベーションの本質
ご紹介する リサーチ・ドリブン・イノベーション - 「問い」 を起点にアイデアを探究する はマーケティングリサーチの本で、興味深く読めました。リサーチの位置づけや認識、方法を良い意味で覆してくれます。
ぜひ最後まで読んでいただき、よかったらこの本を手にとってみてください。
この本に書かれていること
本の内容を一言で言うと、マーケティングリサーチから組織や事業でイノベーションを起こす方法が書かれています。
本書ではそもそもなぜイノベーションが起こりにくいかから話が入り、リサーチを活用したやり方が具体的なリサーチ事例で詳しく紹介されています。協力者としてマーケティングリサーチのインテージ社のデータや社員が、共同プロジェクトに参加していて、プロセスからイメージがしやすかったです。
以下は、本書の内容紹介からの引用です。
いま注目のベンチャーが見つけた、アイデアが生まれるプロセスと場づくりのすべて。
組織開発と事業開発を接続させ、「ボトムアップ型のイノベーション」 に向け、シチズン、サッポロビール、資生堂、京セラなど、各社を支援してきた MIMIGURI 。
これまで数多くの企業と数百件ものワークショップを重ね、リサーチ会社インテージとの共同研究に取り組んできた。イノベーションのプロセスに火をつける、その方法を大公開!
商品開発や商品企画の担当者だけでなく、組織開発・人材開発の担当者、アイデア発想の場づくり、チームビルディング、コミュニティづくりに関心のある方も必読。
読んでおもしろかったこと
この本を読んでおもしろかったのは、次の3つでした。
✓ おもしろかったこと
- マーケティングリサーチからイノベーションへ
- 全ては 「問いの設計」 から始まる
- 多数決ではなく 「多様決」
では順番に3つそれぞれをご説明しますね。
マーケティングリサーチからイノベーションへ
リサーチからイノベーションにつなげるという考え方が、おもしろかったです。
というのも、これは一般的なリサーチのイメージとは逆だからです。よく言われることにマーケティングリサーチ不要論があります。
例えば、携帯電話が今でいうガラケーが主流だった時代にマーケティングリサーチをしても iPhone は生まれなかった、もっと昔では馬車の時代に人々に訊いても自動車という移動手段は出てこなかった、という話です。
ともするとマーケティングリサーチはイノベーションから遠い存在に見られます。イノベーションにはリサーチは不要と考える人もいます。
私自身はリサーチ不要論は違うと思いますが (詳細は以下の記事で書いています) 、リサーチからイノベーションを生む考え方やマインドセット、具体的な方法が体系立てて解説されていて興味深く読めました。
「マーケティングリサーチ不要論」 は違うと思う。リサーチの意義とマーケターの役割
全ては 「問いの設計」 から始まる
では、マーケティングリサーチからどうやってイノベーションを生めるのでしょうか?
ここでは1つだけに絞ると、「問いの設計」 です。
問いとは、リサーチで明らかにする答えや示唆を出すためのリサーチ課題です。本質的で掘り下げる価値がある問いを設定できるかがポイントです。
具体的な問いのイメージを本書で紹介されていた事例からご紹介しますね。
事例は2つで、1つは20代の 「さとり世代」 への保険サービスをつくることでした。リサーチの問いは 「さとり世代にとっての “安心” や “つながり” とは何か」 です。
もう1つの事例はコンビニで新しいサービスをつくるために、問いは 「コンビニ利用者にとっての “便利” とは何か」 です。
通常、保険サービスを考えるときのマーケティングリサーチの問いは 「あなたが欲しい保険は何ですか」 、コンビニであれば 「コンビニにあったらいいと思うサービスは何ですか」 でしょう。こうした表面的な問いではなく、そもそもの 「安心とは」 「つながりとは」 「便利とは」 から問いを設計したのです。
唯一の答えはなく、解釈に幅が出る問いをつくることが 「問いから始める」 では大事です。
多数決ではなく 「多様決」
本質的な問いを選ぶ基準に 「多様決」 (たようけつ) で決めるという考え方がおもしろかったです。
一般的な意思決定の方法は多数決です。多数決では最も多くの人が同じように思うことが選ばれます。一方の 「多様決」 とは、より多様な解釈がされ、賛否が分かれるものを積極的に選びます。
私はここに、イノベーションにつながるヒントがあると見ました。
イノベーションの本質
イノベーションとは、生まれる前は多くの人が気づいていない、または反対されるものですが、一部のわかっている人には見えています。だからこそ解釈や賛否が様々で、意見が分かれます。
イノベーションとは 「未来の当たり前」 です。未来の当たり前とは逆に言えば、現時点で常識ではなく多くの人は気づいてさえいません。
一致者が多い多数決で決めている限りは、未来の当たり前にはなりません。今すでに当たり前になっていることだからです。マーケティングリサーチからイノベーションにつなげるために 「多様決」 で問いや合意形成をするのは、言われてみれば理に適っています。
自分たちにしかできないリサーチ
リサーチドリブンイノベーションを実現するためには、誰がやっても同じリサーチ結果になる方法ではイノベーションにつながりません。
解釈が多様にできる問いに対して、自分たちならではの答えや示唆を出し他者 (他社) との違いをつくります。
そもそもの問いかけがユニークで、問いへの答えに独自性があるほどイノベーションにつながります。「多くの人はそうは思わないが、自分たちにとって大切な真実」 をリサーチから得るのです。これが私が理解したリサーチドリブンイノベーションの本質です。
まとめ
今回は リサーチ・ドリブン・イノベーション - 「問い」 を起点にアイデアを探究する (安斎勇樹, 小田裕和) という本をご紹介しました。
最後に記事のまとめです。
本書の概要
- マーケティングリサーチから組織や事業でイノベーションを起こす方法
- リサーチを活用したやり方が具体的なリサーチ事例から詳しく紹介されている
読んでおもしろかったこと
- マーケティングリサーチからイノベーションへ (一般的なイメージは 「リサーチとイノベーションは結びつきにくい」 で、これとは逆の発想)
- 全ては 「問いの設計」 から始まる
- 多数決ではなく 「多様決」 で決める (解釈に幅があり賛否が分かれるものを採用する)
リサーチドリブンイノベーションの本質
- 誰がやっても同じリサーチ結果になる方法ではイノベーションにつながらない
- 解釈が多様にできる問いに、独自の答えや示唆を出し他者 (他社) との違いをつくる
- 「多くの人はそうは思わないが、自分たちにとって大切な真実」 を得るのがリサーチドリブンイノベーション