
今回は、成功要因を分解して KPI まで落とし込み、ストーリー化する方法についてです。
この記事でわかること
- KPI に落とし込むプロセス
- note の例 (グロースモデルと KPI)
- 目的から KPI 設定までの意味合い
記事の前半では、目的とゴール設定、成功要因の洗い出し、KPI 設計について事例を交えながら見ていきます。
そこから後半は、目的から KPI 設定までの本質、何を意味するかを掘り下げています。
ぜひ記事を最後まで読んでいただき、お仕事での参考にしてみてください。
KPI に落とし込むプロセス
皆さんは普段のお仕事で、何か KPI を使っているでしょうか?
KPI を作るにはプロセスがあります。ポイントは、いきなり KPI に入らないことです。
まず始めに目的を設定します。次にゴールの言語化です。ゴールとは目的を達成した時の状態です。ゴールを評価するための KGI (Key Goal Indicator) を設定します。
次にゴールに到達するための成功要因を洗い出します。これが KSF (Key Success Factor) になります。 KSF を実現するシナリオを描きます。各要素の関係性や時間展開の構造化と可視化です。
この後に KPI です。KSF が実現したかどうかを判断するための指標が KPI です。
ここまでの KPI を作るプロセスをまとめると次のようになります。
KPI に落とし込むプロセス
- 目的
- ゴール (KGI)
- KSF
- 成功シナリオ
- KPI
では具体例に当てはめて見てみましょう。
note の例
皆さんは note を使っていらっしゃるでしょうか?
KPI に落とし込むプロセスを note に当てはめてみます。なおここから書いている note のことは個人的な見解です。
note の目的は、クリエイターが創作活動を続ける機会を提供することです。ゴールは様々なコンテンツが日々生まれている状態です。KGI は日次の新規コンテンツ数になります。
では KSF はどうなるでしょうか?
note の KSF
- アクティブなクリエイターを増やす
- ユーザーにとってコンテンツが有益で楽しく意味がある
- コンテンツ数を見に来るユーザーも増やす
note のグロースモデル
KSF をシナリオにしたものがグロースモデルです。
以下の図が note のグロースモデルです。
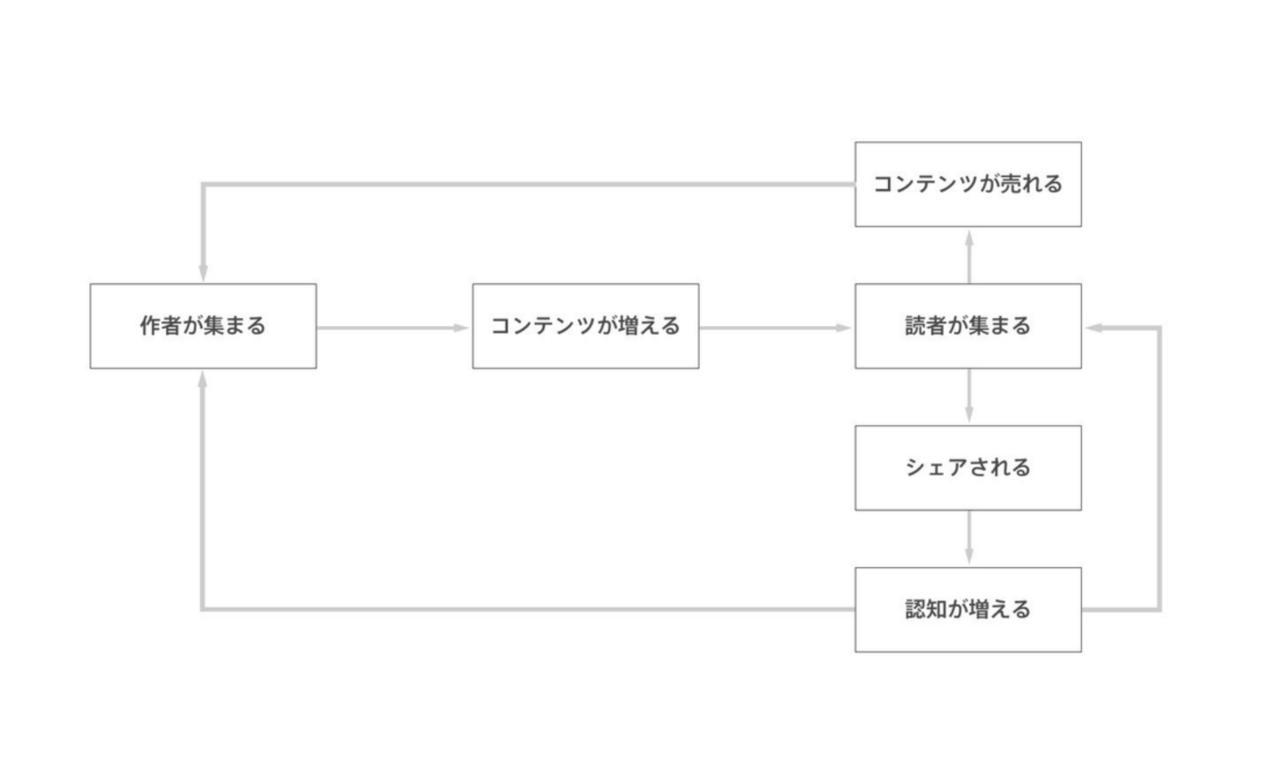
引用: note 急成長の舞台裏と .com .jp ドメイン取得の経緯を聞いてきたよ (第1回) |決算が読めるようになるノート
note が目指しているのは、クリエイターがクリエイティブ活動をできる場所の提供です。
その指針となるのがグロースモデルです。note のクロースモデルのポイントを三つに絞るなら、作り手 (クリエイター) 、コンテンツ、読者です。
note の KPI
ここから、KPI に落とし込みます。
グロースモデルから KPI へ (note の例)
- クリエイター数 (例: 月に1回以上で発信しているアクティブのクリエイター数)
- 訪問者数 (例: 月間でのログイン者数と非ログイン者数)
以上の note の KPI 設計はあくまで私の見解ですが、クロースモデルから整合性があり、良い KPI の条件である 「シンプル」 「構造化」 「測定」 を満たしています。
これらを追うべき指標に設定し、そのためにどんなアクションを実施するか、各施策がグロースモデルのどこに寄与したかを見ていきます。グロースモデルと KPI が連動します。
目的から KPI 設定までの意味合い
ここまで見てきたことは、要するにどういうことなのでしょうか?
成功要因の解像度を高めるために因数分解をしました。各要素の相互作用や時間展開を可視化しストーリーとして描きました。可視化の例は先ほど見たグローブモデルです。
解像度を高くしておけば、現状を詳細に把握することができます。打ち手が具体化し検証や評価もしやすくなります。改善ポイントが明確になります。
以上の積み重ねが成功確率を高めるのです。
まとめ
今回は目的から KPI に落とし込むプロセスを掘り下げ、解像度高く成功要因を見出す方法をご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
最後に今回の記事のまとめです。
KPI に落とし込むプロセス
- 目的の設定
- ゴール (KGI) を描く
- KSF を見出す
- 成功シナリオをつくる
- KPI に落とし込む
目的から KPI 設定までの意味合い
- 成功要因の解像度を高められる
- 解像度を高くしておけば、現状を詳細に把握できる
- 打ち手が具体化し検証や評価もしやすく、改善ポイントが明確になる