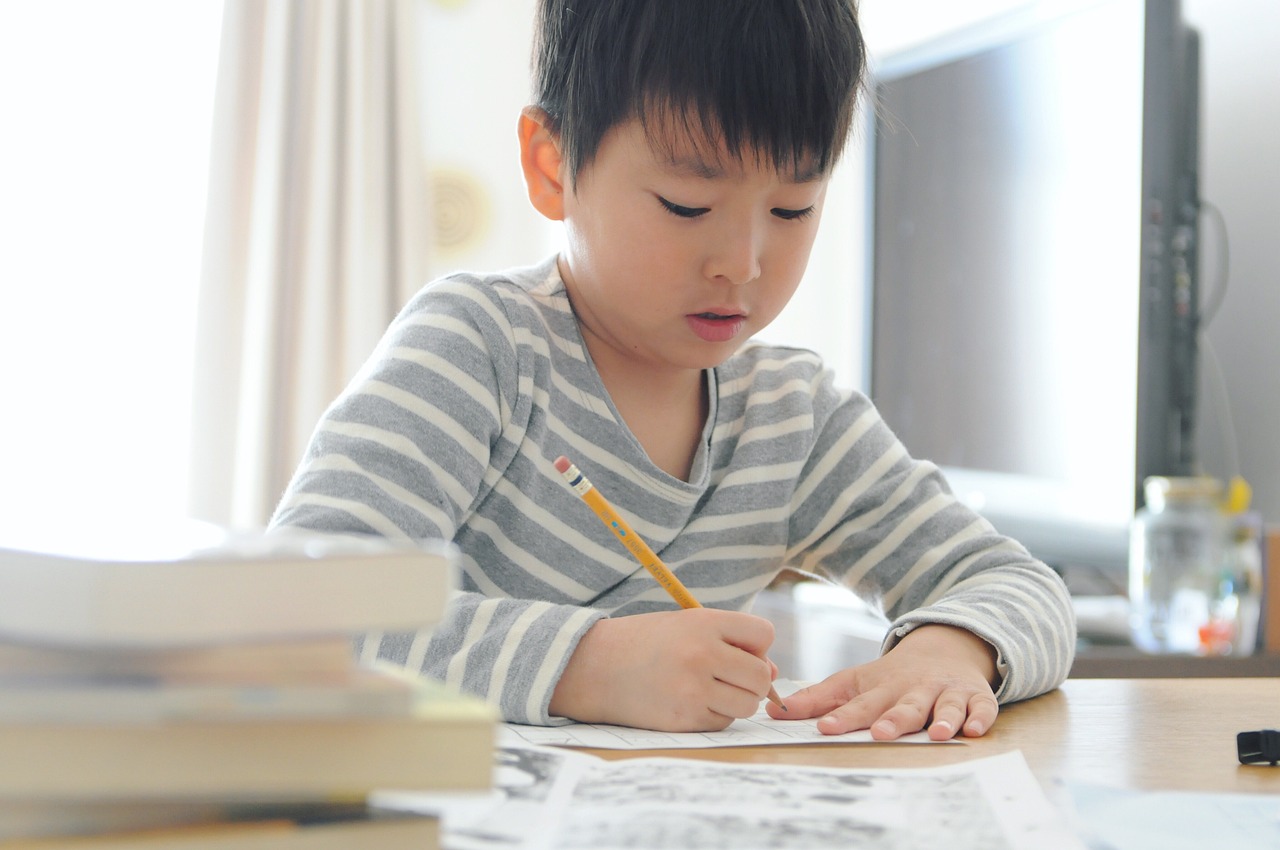今回の読書についてです。読書方法や本を読むことの意味合いです。
✓ この記事でわかること
- 苦手だった読書感想文
- なぜ嫌だったのか?
- 小学生の自分に伝えたいこと (読書方法と意味合い)
本の選び方や読書方法に、少しでも参考になればうれしいです。
苦手だった読書感想文
私が小学生だった時、苦手だったことの1つが読書感想文でした。
夏休みの宿題で必ずと言っていいほど後回しになっていました。あらためて今思い返すと、読書感想文に苦手意識を持っていた理由は3つです。
✓ 読書感想文が苦手だった理由
- どの本を読んでいいかわからない
- 何を書いていいかわからない
- 原稿用紙に書くのが面倒に感じる
夏休みや冬休みで、読書感想文は最後になって仕方なく取り掛かっていました。
小学生の自分に伝えたいこと
大人になった今では、ブログや note に読んだ本を書評という形で書いて発信をしています。子どもの頃の自分からすると想像できないことです。
今だからこそ言える、小学生だった自分に伝えたい読書方法や本との向き合い方があります。
✓ 小学生の自分に伝えたいこと
- いきなり原稿用紙に書き始めない ( 「考える」 と 「書く」 を分ける)
- 読書とは自分との対話
- 読書に正解はない
ではそれぞれについて順番にご説明しますね。
いきなり原稿用紙に書き始めない
1つ目に小学生の頃の自分に伝えたいことは、読書感想文で 「いきなり原稿用紙に書き始めないこと」 です。
これが意味することは、「考える」 と 「書く」 を分ける重要性です。順番はまず先に考えて、その後に原稿用紙に書き始めます。
小学生の時の読書感想文に良い思い出がないのは、いざ原稿用紙に書き始めようと思ってもすぐに手が止まって書けなくなる体験からです。書きながら考えるという、いわばマルチタスクで複数のことを同時にやっていたわけです。
そうではなく、原稿用紙に書く前にあらかじめ書く内容を整理しておくといいです。具体的には、読んで印象的だったこと、思ったこと、考えたことを自由帳やプリントの裏に頭から吐き出すように書き出します。
この時点ではまとまっていなくてもよく、雑でいいので書いていくと少しずつ頭の中が整理できます。書くことが整って初めて原稿用紙に書いていきます。
読書とは自分との対話
2つ目の子どもの時の自分へのメッセージは、読書の捉え方です。読書とは 「自分との対話」 です。
読書感想文のことを文字通りの 「感想文」 と思っていて、おもしろかった、良かったくらいしか書けませんでした。
やるといいのは、本を読んで自分が感じたことや思ったこと、気づきの掘り下げです。何がそう思わせたのか、なぜそう感じたのかですです。つまり本というネタをきっかけに、自分自身との会話です。
自分との対話のキャッチボールから自分の感情や意見をつくっていきます。
読書に正解はない
今思えば、読書感想文に 「正解」 を求めていました。正解に囚われすぎていました。
正解を分解すると3つあり、選ぶ本、読み方、感想内容です。担任の先生やクラスメイトの目を気にしすぎていたわけです。
読書に正解はなく、十人十色です。自分だからこそ書けることを素直に書けばいいんですよね。
自分が気になって選んだ本を、自由に読み、書くことも自分が感じた・思ったことをそのまま書けばいいです。
まとめ
今回は読書についてでした。
最後に記事のまとめです。
小学生の時に読書感想文が苦手だった理由
- どの本を読んでいいかわからない
- 何を書いていいかわからない
- 原稿用紙に書くのが面倒に感じる
小学生の自分に伝えたいこと
- いきなり原稿用紙に書き始めない ( 「考える」 と 「書く」 を分ける)
- 読書とは自分との対話 (なぜそう感じたか・思ったことを掘り下げる)
- 読書に正解はない (読む本, 読み方, 思ったことは十人十色)