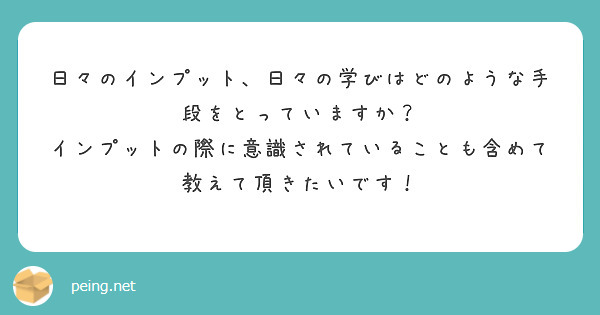今回は、インプットや学びでの方法をご紹介します。
✓ この記事でわかること
- アウトプットありきで学ぶ方法
- 1. 思い出す 「想起」
- 2. 自分の言葉で言い直す 「再言語化」
- 3. すぐに使ってみる 「実践」
今回は日々のインプットや学びで、どのような方法をしているかを紹介します。ポイントはアウトプットです。
ぜひ最後まで読んでいただき、少しでも参考になればうれしいです。
いただいた質問
質問箱の Peing に質問をいただきました。
質問は 「日々のインプットや学びで意識していることは?」 です。
アウトプットありきで
答えを一言で言うなら 「アウトプットありきでインプットする」 です。
インプットの前、最中、そして後で、常にどう活用するかを意識しています。
インプットからアウトプットへの要素分解すると、次の3つです。
✓ インプットで意識していること (三段階のアウトプット)
- 思い出す 「想起」
- 自分の言葉で言い直す 「再言語化」
- すぐに使ってみる 「実践」
では、3つを具体例も入れながら順番にご説明しますね。
[ステップ 1] 想起
インプットしたことを思い出す機会をつくります。
思い出す回数や機会が多いほど記憶に定着しますよね。
具体例に当てはめると、例えば読書です。
読書中に区切りのいいところ、例えば1つの章を読み終わったら本を閉じ、キンドルなら画面をスリープにし読んだ内容を振り返ります。具体的には 「この章のポイントを3つにまとめると」 と自分に問いかけてみるといいです。
仕事での専門領域の勉強で私がやっているのは、読んでいる最中だけではなく翌日、3日後、1週間後と定期的に思い出す機会をつくっています。
[ステップ 2] 再言語化
2つ目のステップが自分の言葉で言い直してみる 「再言語化」 です。
インプットしたことへの自分の理解を言葉で表現してみます。ポイントは書かれていた・聞いたことをそのまま暗記するのではなく、自分の言葉で言い換えます。
再言語化のプロセスで理解が深まり、記憶としても強化されるんですよね。
読書の例で続けると、1つ目の 「想起」 の時に書いてあった内容をそのままではなく、自分の言葉で言い直してみます。
まわりに人がいなく可能なら、独り言のように口に出してその場で話してみるといいです。話すだけではなく紙に書くのも効果的です。
[ステップ 3] 実践
3つ目のステップはインプットしたことを自分で使ってみる 「実践」 です。
実際に活用する機会をつくるといいです。
例えばインプットしたことを人に説明をしてみます。もし直接伝えたり教える相手がいなければ、頭の中で相手をイメージして説明をしてみてください。この時にあまり詳しくない人を選んでみましょう。例えば部署の違う同期、家族、友人です。
読書に当てはめれば、本から学んだことを同僚との雑談に話題として入れてみます。他には、すぐに仕事で試してみる、会議で引用する、企画や提案の中に使ってみるといいですよ。
実際に仕事で使おうとすると、理解ができているところと曖昧な部分がわかるんですよね。理解が十分でないところは次のインプットにつながります。
インプットや学びの前や最中から、虎視眈々と狙うようにどんなアウトプットができるかを常に具体的に意識してみるといいです。
まとめ
今回は、日々のインプットや学びで意識していることでした。
最後に記事のまとめです。
日々のインプットや学ぶで意識していること (三段階のアウトプット)
- 思い出す 「想起」 の機会をつくる
- 自分の言葉で言い直す 「再言語化」 。人に説明してみる
- すぐに使ってみる 「実践」 。例えば仕事で使ってみる
- インプットや学びの前や最中から、どんなアウトプットができるかを常に具体的に意識してみよう